キリスト教の教えに対する統一原理の見解サイトに掲載されている記事を紹介します。
キリスト教神学に対する統一原理の見解を解説しているサイトで、
今回はスイス出身で、プロテスタントの神学者ブランナーの「出会いの神学」の連載8回目です。
下記はサイトより一部引用です。
ブルンナーは、「神の像」という視点から、男と女の関係を次のように考察している。
「人間創造は、相手ができるまでは、完成されていない。……神は愛であり、神の本質自身に交わりが存在する故に、人間は愛することができる者として、一対の人間として、造られねばならない。彼は他者なしには自己の本質を実現することはできないのであり、その目ざす所は、愛における交わりである。」(『ブルンナー著作集』第3巻 教義学Ⅱ、教文館、1997年、79頁)
このように、ブルンナーは、「神は愛であり、神の本質自身に交わりが存在する」と述べ、「神の似姿」とは男と女に分かれていることではなく、「一対の人間」(二人は一体)であると原理的に捉えている。しかし、「一対の人間」から、愛なる神を二性性相の中和的主体と捉えるに至っていない。また、二人(アダムとエバ)の愛の成長過程についても述べていない。
これに対して、バルトは神を「三位一体の神」と捉え、その神(神論)から人間との縦的関係と、人間と人間との横的関係を基本形として捉え、男と女の区別と関係について述べている。
それで、ここから、バルトの「神の像」(男と女)の解釈を中心に論述していくことにする。
バルトは、人間の応答責任について次のように述べている。
「人間は、創造主なる神の前で応答の責任をとる間に、存在する。そのことは、あれらの線のうちの第一の線であり、それを念頭においてわれわれは神の誡めを前節で、この応答責任を遂行し、そのようにして神の前で、神のために、自由であるようにという誡めとして理解しようとこころみた。人間についてあの第一の命題から、今、次の第二の命題が区別されなければならない。それはすなわち、人間はその創造の中で、創造と共に、したがって彼が人間として存在することがゆるされる間に、神の契約相手であるよう定められており、この彼の定めが彼の存在をほかの人間との出会いの中での存在として特徴づけているという命題である。人間が、神との契約の中で存在するよう定められているということ、そのことはその対応を、彼の人間性(Menschlichkeit)、すなわち、彼の存在の特別な性質は、もともと、はじめからして、そのようなものとして〔隣人と〕共なる人間性(Mitmenschlichkeit)であるということの中に、その対応をもっている。」(カール・バルトの主著『教会教義学 創造論Ⅳ/2』吉永正義訳 新教出版社、1980年、3-4頁)
このように、バルトは「神の像」から、第一の命題として、人間は「神の契約相手」(縦的関係)であるように定められていると述べ、第二の命題として、「〔隣人と〕共なる人間性」(横的関係)として、他の人間との出会いの中での存在として定められているというのである。
同様のことであるが、またバルトは、「神は人間に対しその人間性に向かって語りかけ給う。そのことは具体的には、神は人間をその隣人に向かわせ給うということを意味している。……神は人間を、『交わりの中での自由』へと、すなわち、その隣人との交わりの中での自由へと、呼び入れることの中で、神との契約の中にあるべしという人間の定めにおいて、真剣に受けとり給うということを意味している」(同、4頁)と述べている。
このように、神と人間との縦的な関係は、孤立した関係ではなく、人間と人間との横的関係性として定められているというのである。これが人間の基本的形態で、それは男と女の関係で示されるというのである。
次に、バルトは「隣人と共なる人間性」を通じて「神を知る」と、下記のように述べている。
「神は人間を、彼がほかのものを肯定する間に、自分自身を知り、ほかのものを慰め励ます間に、自らを喜び、ほかのものを尊重する間に、自分自身が自分であることを実証するよう呼び出し給う。この自由への呼び声として――(われわれはまたこのように言うことができる)人間性(Humanität)への呼び出しとして――われわれは今、神の誡めを理解しなければならない。人間性、人間的存在の特別な、自然的な性質は、その根において、まさに隣人と共なる人間性である。隣人と共なる人間性でないような人間性は非人間性(Unmenschlichkeit、Inhumanität)であるであろう。そのような〔隣人と共なる人間性でないような〕人間性は、また神の契約相手であるべき人間の定めに対応することができず、ただ矛盾することができるだけである。その間の事情は、ちょうど孤独ナ神ではなく、三位一体ノ神、関係の中での神、であり給う神が、孤独ナ人間の中に、ご自身を再認識し給うことができないのと同じようである。神が人間に対して人間性を、したがって交わりの中での自由を、命じ給う間に、神は、人間に対して、自分自身を神の似像として――なぜならばそのようなものとして神は彼を創造されたのであるから――確証し、実証するよう呼び出し給う。そのことが、われわれが今考察しなければならない神の誡めの形態の最も深い、最後的な基礎づけである。」(カール・バルト著『教会教義学 創造論Ⅳ/2』吉永正義訳 新教出版社、1980年、4-5頁、注:太字ゴシックは筆者による)
そして、バルトは、「隣人と共なる人間性の最初の、同時にまた範例的な領域、人間と人間の間の最初の、同時にまた範例的な区別と関係か、男と女の間の区別と関係である」(同、5頁)と述べている。
このように、バルトは、「神の像」を「隣人と共なる人間性」(共同人間性)として理解するのである。つまり、バルトは「神の像」(男と女)を「三位一体の神」の似像として類比的に理解しているのである。
言い換えると、「神が、孤独ナ人間の中に、ご自身を再認識し給うことができない」といい、神は、「隣人と共なる人間性」(男と女)を通じて「確証し、実証するよう呼び出し給う」と述べ、神と人間との「類比の関係」から、神を知ることができるというのである。
このように、バルトは、神と人間との関係を類比的に捉えているが、この類比については、ブルンナーはバルトに対して次のように述べていた。
「バルトの教義学も、そのほかのすべての教義学と同じようにアナロギア(Analogie)の思想の上に基礎を持っている。ただ、バルトはそのことを認めようとしないだけである。」(『自然と恩寵』170頁)。
しかし、バルトは、反論文『ナイン!』では沈黙していたが、『教会教義学』においてブルンナーとの論争を省察し、上述のように〝神の像〟の解釈を展開しているのである。
ただし、バルトは、神と人との関係をトマス・アクィナスのように「存在の類比」と捉えるのではなく、信仰の義認によって新しく形成される神と人間との関係、すなわち「関係の類比」(信仰の類比)として捉えるのである。つまり、自然神学の立場から、人間は「神の像」であると「存在の類比」として捉えることを否定しているのである。
しかし、カトリック側から、バルトの「関係の類比」(信仰の類比)は「存在の類比」が前提でそのように言えるのではないかと反論されている。
ところで、文鮮明師は、神と人間(アダムとエバ)との縦的な「真の愛」の関係と「男と女」(アダムとエバ)の横的な「真の愛」の関係において、二人の「真の愛」の成長過程を捉え、「四大心情圏」と「三大王権」として解明されている(図解がある)。
バルトの「神の像」の解釈は、この真理をキリスト教会が受容することを可能にする前提条件となるであろう。
以上のように、バルトは「三位一体の神」の内在的関係(父、子、聖霊がどのような相互関係にあるかということ)から出発して、共同人間性を理解し、共同人間性を前提として男と女の関係を理解し、隣人と共なる人間性の最初の範例的な区別と関係は、男と女の間の区別と関係であると述べているのである。
ただし、最初の範例的な区別と関係の成長過程に関しては、ブルンナーと同様に論じていない。バルトは「三位一体の神」というが、イエスに幼年―少年―成人という成長過程があったように、神に〝成長〟という概念があることを知らないのである。したがって、バルトは「成長過程」において、「真の家庭」の中で、神の愛を確証し、「四大心情圏」と「三大王権」として原理的に解明していない。バルトやブルンナーは再臨のメシヤでないので、それは致し方がないことである。
続きはキリスト教の教えに対する統一原理の見解サイトに掲載されています。
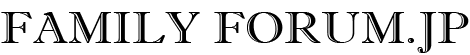




コメント