国際勝共連合オピニオンサイトRASHINBANに新しいオピニオンがupされていたのでご紹介いたします。
なぜ沖縄に米軍基地が集中しているのか?
面積にすると、在日米軍使用施設全体の33%が北海道にあり、22%が沖縄にあります。北海道は広大ですから、沖縄の割合が極めて高いことになります。沖縄県全体の面積に対しては10.4%を占めています。
※ ただし沖縄県がHPで「国土面積のわずか0.6%に過ぎない狭い沖縄県に、在日米軍専用施設面積の約74%に及ぶ広大な面積の米軍基地が存在しています」と掲載しているのは、基地問題を正しく説明していません。日本では、自衛隊と共用基地とする米軍基地が多数あり、これを省いているからです。沖縄における在日米軍「専用」基地の割合は確かに74%ですが、総面積では22%です。
ではなぜ沖縄に基地が集中しているのでしょうか。それは反対派が言うように、「政府が沖縄を差別しているから」ではありません。沖縄が安全保障上、極めて重要な地域だからです。
日本周辺で潜在的な紛争地域と想定されるのは、朝鮮半島と台湾です。そしてこれらの地域に最も近いのが沖縄です。また、日本はエネルギーのほとんどを輸入に頼っていますが、その大半が沖縄周辺を通過します。詳細は、平成27年度版防衛白書の図で確認することができます。
これらの地域で紛争を防ぐには、「強力な軍事力がすぐに駆けつけることができる」体制を整えなければなりません。たとえば国内で事件が起きて警察に通報しても、駆けつけるのに1時間もかかるのであれば犯罪の抑止力としては不十分でしょう。同様に、沖縄に強力な米軍が駐留していることは、日本やアジアの平和と安全にとって極めて重要なことなのです。
このことについては裁判所も、「海兵隊航空基地を沖縄本島から移設すれば海兵隊の機動力・即応力が失われることになるから採用することができない」(福岡高裁那覇支部の判決要旨、2016年9月16日)と明言しています。判決文はこちらから確認できます。
もちろん政府が沖縄の負担軽減のために、最大限の努力をしなければならないのは言うまでもありません。そしてその最大の取り組みが、現在行われている米普天間飛行場の辺野古への移転計画です。この計画が2013年に沖縄県に提出された際には、仲井眞弘多知事(当時)が「驚くべき立派な内容だ」と評価し、承認しました。
現在の翁長雄志知事は、この計画に徹底して反対しています。また、多くのマスコミが翁長氏側に立って報道しています。彼らの言動に惑わされず、しっかりと事実を認識しなければなりません。
RASHINBANの記事はコチラ
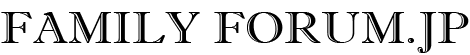



コメント