グーグルはなぜ働きがいがあるのか
震災後の調査から見えてきた3つのカギ
2012年2月28日(火)
1/4ページ
働きがいのある会社を作ろうと努力している経営者は少なくない。だが、人の心は十人十色。万人が満足する企業風土を作り上げるのは並大抵のことではなく、仮に実現したとしても、業績悪化や社内制度の変更などでたやすく失われてしまう。そんな脆くて壊れやすい働きがいだが、ひとたび従業員が感じれば、その能力の総和以上の力を生み出すことも可能となる。
会社のプレゼンよりも従業員の声を重視
それでは、働きがいのある会社とはどのような会社なのだろうか。それを検証するため、日経ビジネスでは2007年以降、「Great Place
to work? Institute Japan(GPTWジャパン)」(contact@greatplacetowork.jp)の協力を得て、「働きがいのある会社」という企画を続けている。米国のGPTW本部は、米経済誌「フォーチュン」が毎年掲載している「100
Best Companies to Work for」に調査データを提供している団体。それと同じ手法をGPTWジャパンも採用している。
GPTWでは、「従業員が会社や経営者、管理者を信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感を持てる会社」と働きがいのある会社を定義づけている。その要素として「信用」「尊敬」「公正」「誇り」「連帯感」の5つに分類している(右図)。これは、この調査を生み出したロバート・レベリング氏が分類したものだ。従業員と経営者の信頼関係、フェアな企業体質、同僚や上司との関係――。ほかの分類もあるだろうが、働きがいを構成する要素と言われても特に違和感はないのではないか。
この調査の特徴は徹底した従業員目線という点にある。社内制度や企業文化などに関する企業への質問と従業員に対するアンケートをGPTWジャパンの評価委員会が読み込み、5要素ごとに点数をつけていく。合計点に占める従業員アンケートの割合は3分の2。回答する従業員もGPTWジャパンが指定した方法で無作為に選ばれる。ほかの従業員満足度と大きく異なるのは、会社のプレゼンよりも従業員の声に焦点を当てているところ。これだけ従業員目線の調査はそうそうない(調査の概要はこちら)。
もっとも、その代償として、調査に手を挙げた企業以外は調査の網にかからない。参加企業を募集している段階で東日本大震災に見舞われた2012年版調査には123社が参加した。その前年は151社。これを多いと見るか、少ないと見るかは人それぞれだが、従業員目線の調査にあえて参加してくるのは、それだけ従業員の働きがいと真剣に向き合っているということだろう。
2012年版調査のトップはグーグル
さて、前置きが長くなったが、2012年版の結果を見ていこう。前述した通り、2011年7~11月に実施した今回の調査には123社が参加し、従業員が250人未満の企業を含めて40社が「働きがいのある会社」という評価を受けた(GPTWジャパンでは、従業員250人以上と250人未満で分けている。250人以上の大企業版では83社が参加し30社が選ばれた)(下図)
この2012年版で1位に選ばれたのはグーグルだ。「信用」「尊敬」「公正」「誇り」「連帯感」のすべての要素で最高点をマークした。実は、2011年版調査でもグーグルは1位に輝いており2年連続の快挙となった。それは親会社の米グーグルも同様で、フォーチュンの調査で2007年、2008年、2012年と3回にわたって1位を獲得している。
なぜグーグルの従業員は働きがいを感じているのか。その理由は従業員によって様々だろうが、大きく言って以下の3つに分類できると思う。
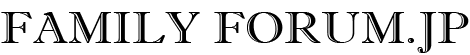





コメント